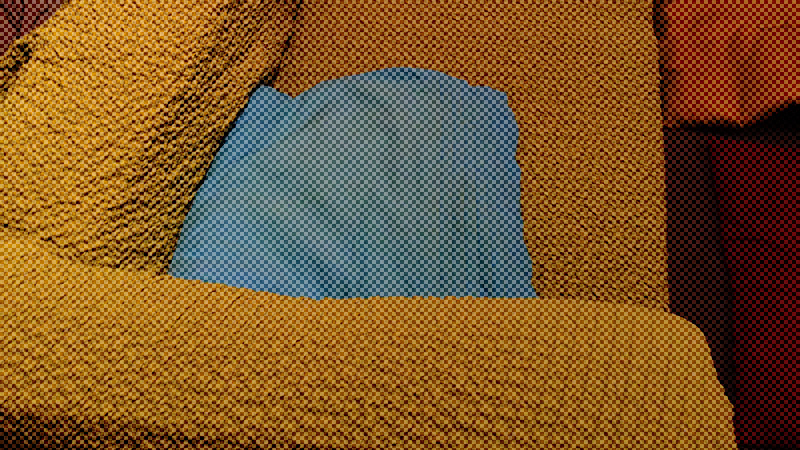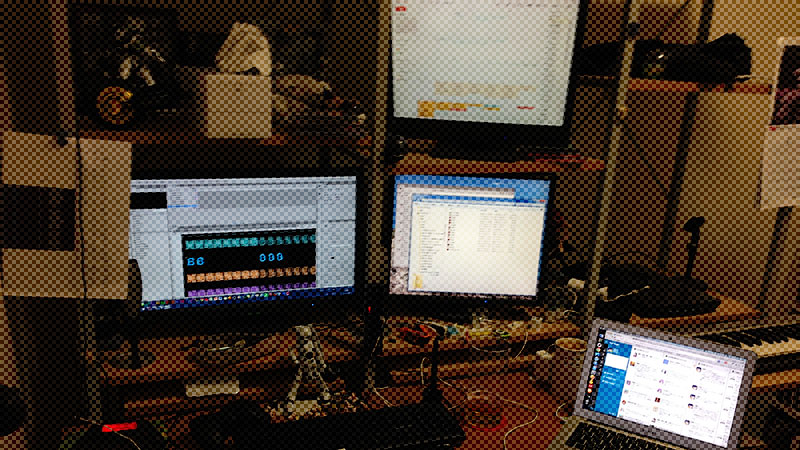調子が崩れてきたなら休めばいいじゃないかと思うことだろう。至極当然のことではあるが、実はこれが難しい。
少なくとも私は休むのが上手ではない。染み付いた癖はなかなか抜けないものなのだ。
ちょっと考えれば簡単そうなのに、いざ自分のこととなるとすごく難しいのが「休もう」という判断。
「どうして休むのが難しいのか?どうやったらうまく休めるのか?」そのあたりをチェックリストを作らずにはおれない私が考察していく。
なにをもって「調子が崩れてきた」と思うか
それは恐らく、なにか決めていることができなくなってきたときではないかと思う。つまり、チェックリストのチェックがつかないことが多くなってきたときだ。
例えば、朝6時半に起きると決めていたのが、だんだん時間が遅くなってきて7時半になってしまったり、週3日は運動をしようとしていたのが、今週は1日も運動できなかったという状態だ。
さて、どうだろうか?
「調子が崩れてきた」という言い方あれば休めばいいと思うかもしれないが、「起きれなくなってきた」であれば、「起きれるように頑張ろう」とはならないだろうか?下手をすると「ここが頑張りどころ」とばかりに無理をしてしまうこともあるだろう。
これが休めない癖というものである。非常に手強いことが分かるだろう。チェックをつけたいという衝動は、割りと大きいのだ。
チェックリストは悪く無い
こうしてみると、なにができたかできないかを管理するチェックリストは、なんだか悪いもののように感じてしまうかもしれない。
日々のチェックリストは目下の進捗や状態を管理するのに長けてはいるが、できたかできないかを視覚化できるため、現実をつきつけられるという点で、改善を迫られているように感じることもあるだろう。
だからといって、チェックリストを捨ててしまうことはない。
すぐにチェックリストにしてしまうという特性が私にはあるが、そうであればこそもっとチェックリストを正しく活用すべきだと思う。
現実との向き合い方
チェックリストがつきつける現実との向き合い方のコツは、チェックリストは改善を迫っているのではなくて、今の状態を教えてくれているものだと捉えることだ。決して責めているわけではない。(しかし責められているという気持ちはなかなか消せないので、これこそ頑張って自分に言い聞かせて見方を変えよう。)
業務の進捗管理表であればそれはリカバリが必要であったりするのかもしれないが、自分の生活行動のチェックリストは、人に見せなくてはいけないものではないし、そのチェックリストがチェックで埋まることで幸せになれるわけでもない。
チェックリストがはかばかしくないとき、それは休養のサインだ。
チェックリストがはかばかしくないのであれば、調子が悪いのだろう。調子が悪いのなら休まなくてはいけない。
求められているのはチェックを付けられるようにするために頑張るのではなく、チェックをつけられるように休むことだ。(もっといえば、自分以外のだれもチェックをつけることをもとめてはいないのだが)
もし、そのチェック項目が新しいもので、いままでうまくやれた実績がないのであれば、単にハードルが高かっただけなのかもしれない。チェック項目自体も見なおす必要があるだろう。
チェックリストは何のため?
いまよりよくするために、課題をあげて、一つ一つこなせるようにするためのもの・・・だと私は思っている。
つまり、息をするようにできて当然のものはチェックリストにはあがってこないということだ。良いチェックリストならば、いまの自分には少しだけ難しい項目が並んでいることだろう。
裏を返せば、全部チェックがつかなくても何かができなくなったわけではないのである。
できそうでできないものだからチェックリストにあがっているのだ。つまり、ムラが出やすい項目をピックアップしているわけだ。
これは自分だけの最適化された「調子をみるための材料」なのではないだろうか?
そもそもチェックリストを作ったのは、「自分の成長が見えるようにすれば達成感が得られるのではないかと考えて、これが正解かはわからないけれどとにかくやらずにはおれなかった」といったことではないだろうか?
達成感という点でみれば「それは不正解」だ。
デイリーのチェックリストでは、監視はできても達成感はなかなか得られない。伸び盛りの青少年ではないのだから、チェックで埋まることもそうそうないだろう。埋まったところでそれはかりそめだ。自信にはつながらない。
やらずにはおれなかったチェックリストの本当の活用法は、「調子をみるための材料」だと割りきってしまおう。生活を見直すための指標だ。乱高下するほど良いチェックリストというわけだ。
最後に
偉そうに書いているが、このチェックリストの本当の活用法を見つけたのはつい最近のことだ。こうして文章におこすことで、気付きが確証に変わったといっても過言ではない。
自分ができるかできないかの境界を監視することで、異常の初動をいち早くつかむセンサーとしての機能をもつのがチェックリストと考えれば、更新する意味も続ける意味も出てくる。
チェックリストは、当初の「達成感を得るためのツール」としては使えない。
しかしながら、数値目標などで得られる達成感は薄っぺらい。実はこういう地道な活動を丁寧に続けることで、あるときふと「よく考えたらコツコツ頑張ってここまできたよねぇ」とふつふつとこみ上げてくるのが本物である。そしてそれが自信にもつながる。
「正解かどうかは分からないけれど、やらずにはおれない」というものの近くに自分なりの答えはあるはずだ。
やりたい行動を安易にやめるのではなく、活用方法を考えるというアプローチが、楽しく成長できる一つの答えではないかと思う。