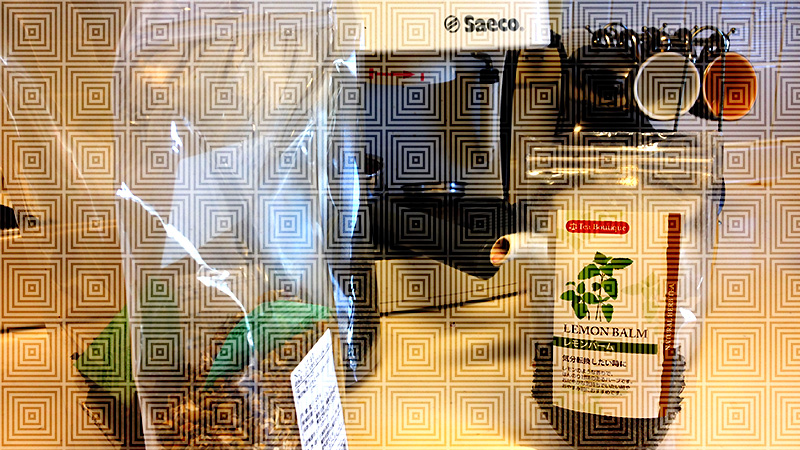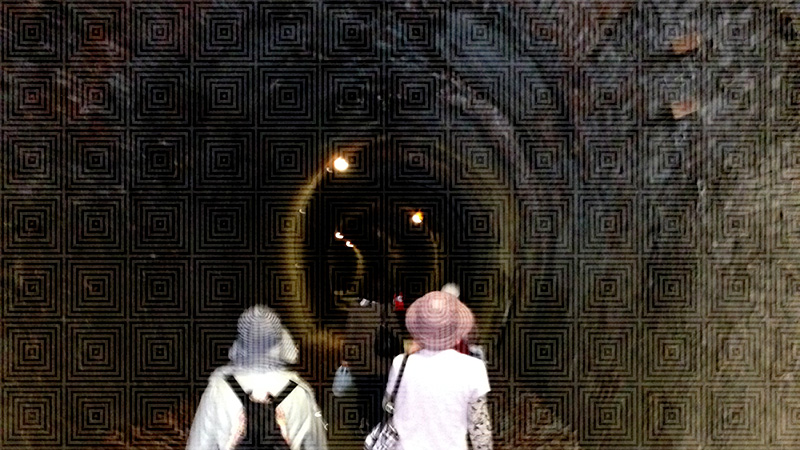パラダイムシフトは認識しないとおこせない
もはやバズワードの感もある「パラダイムシフト」。
パラダイムとは枠組みのことであり、つまりパラダイムシフトというのは、自分の既成概念をガラリと変えてしまうということなのだが、その真骨頂は見方が変わるところではなくて、それによって人生が変わることにある。
そんな話も本を読まなければ分からない。
抽象的な概念を理解するには、読書の力は欠かせないと思う。読書をしていないと「抽象的な概念」というアプローチを理解することも難しいと思う。
外からの風が必要
自分を客観的にみるには、周りの話だけではなかなか難しい。インターネットだけでも難しい。
自分の周りの人というのは、自分の世界の構成員であり、自分の世界観が少なからず通じる人たちである。そしてそれは、いわゆるステークホルダー(利害関係のある人たち)であり、腹を割って話すリスクが大きい。
また、インターネットの検索は、自分の知っている自分の世界観の言葉でしか検索をしない。つまり、検索をした時点でフィルタリングされているのだ。
いささか乱暴ではあるが、インターネットの検索と同じ論調で「自分の周りの人たち」を捉えると、それは自分が選択した人たちとも言える。相手が親の場合であっても、親のパラダイムを濃厚に受け継いでいることは否定できないだろう。
こういった自分の周りという枠組みを越えた概念は、書籍でもたらされることが多いのだ。
雑念を抑える
本を読む間、頭の中で声が聞こえるだろう。速読をする人はどういう感覚だかわからないが、少なくとも本を読むには集中力が必要だ。
つまり本を読んでいる間は、他のことを考えにくいのだ。もちろん、本をほっぽらかして別のことを考えてしまうこともあるだろうが、そのときは本の内容が全然頭に入っていないはずだ。
いろんな不安や感情が込み上げてくるときに本をひたすら読むというのは、間違った方法ではないのだ。
本には読み方がある
あなたは月にどのくらいの本を読むだろうか。そして、精読したり、繰り返し読んだり、ささっと読んだりと本によって読み方を変えているだろうか。読み方を使い分けるという意識を持って、読んでいるだろうか。
運動でもお絵描きでもピアノでもなんでもそうなのだが、質を求める前にある程度の量が必要となる。少なくとも十分な量をこなすという経験がないと、質をあげるという感覚がつかめないというのが、何かを習得するときのおよその定説だろうと思う。
数冊並行して読んだり、同じ本を繰り返し読んだり、色々あるだろうが、月に10冊程度は読んでいないと、ちょっと足りないと言わざるを得ない。
それこそ、本の読み方について書いてある本を読んでもいいと思う。読むときの意識の違いで、効果は全然違う・・・のだけど、そういう本をまずは読まなくてはいけない。